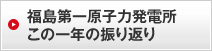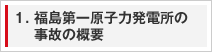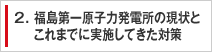1) 事故はどこまで収束したのか
平成23年12月、政府の原子力災害対策本部は「ステップ2完了」を宣言しました。宣言を判断した主な根拠は、原子炉の状態が「冷温停止状態」に到達したことです。「冷温停止状態」とは、①「圧力容器底部、格納容器内それぞれの温度が概ね100℃以下になっている状態」、②「放射性物質の放出量を大幅に抑制し、放出を管理できている状態」、③「原子炉の循環注水冷却システムの中期的安全が確保されている状態」が全て達成された状態です。
①圧力容器底部、格納容器内それぞれの温度が概ね100℃以下になっている状態
1号機から3号機までの圧力容器底部、格納容器内の温度は図5.図6.のグラフのように概ね100℃以下になりました。
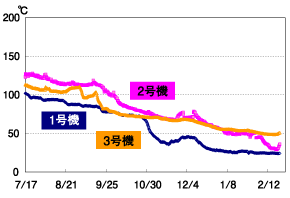
図5. 原子炉圧力容器底部温度
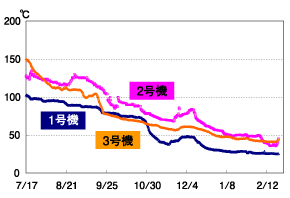
図6. 格納容器気相部温度
<2号機の温度計指示値の上昇について>
平成24年2月上旬、2号機圧力容器底部の温度計1箇所で指示値の上昇が見られました。実際に局所的に温度が上昇しているのか、あるいは温度計の故障なのか、両方の可能性を調査してきました。段階的に原子炉への注水量を約2倍まで増加させて、原子炉の冷却を継続しながら、温度の推移を監視しました。
その結果、圧力容器や格納容器内の他の温度計が注水量の増加に伴って温度が低下していることに比べて、当該温度計の指示値の上昇が続いたこと、電気回路を点検した結果、通常よりも高い抵抗値が測定されたことなどから、当該温度計の指示値の上昇は故障が原因であり、実際の圧力容器底部は十分冷却されていると判断しました。
また、格納容器内の気体のサンプリングを適宜行った結果、再臨界しているかどうかを判断する指標となる放射性物質「キセノン135」が検出限界未満であったことから、再臨界はしていないことを確認しました。さらに、原子炉建屋から放出されている放射性セシウムの濃度についても、温度上昇以前と比較して変化していないことを確認しました。
福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について(平成24年3月2日)
福島第一原子力発電所2号機における一連の原子炉圧力容器底部温度上昇事象を踏まえた今後の原子炉注水量操作について(平成24年2月17日)
福島第一原子力発電所第2号機原子炉圧力容器底部における温度上昇を踏まえた対応に係る報告書の経済産業省原子力安全・保安院への提出について(平成24年2月15日)![]()
②放射性物質の放出量を大幅に抑制し、放出を管理できている状態
大気への放射性物質の放出量(単位時間当たり)は、注水をコントロールすることにより格納容器内の蒸気の発生が抑えられ、図7.のグラフのように、事故直後と比べ約八千万分の一(平成24年2月)と大幅に抑制されるようになりました。また、外部への放射性物質放出量をより管理・抑制できるようにするために、順次、格納容器ガス管理システムの運用を開始しています。(詳細は『 2. 2) 大気への放出抑制対策 』をご参照下さい。)
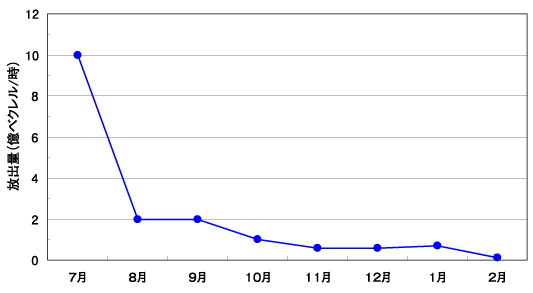
図7. 1~3号機格納容器からの放射性物質(セシウム)の単位時間当たりの放出量
③原子炉の循環注水冷却システムの中期的安全が確保されている状態
原子炉の循環注水冷却システムについては、原子炉注水ラインの一部あるいは全体の故障に備えた予備の配管や水源、ポンプ等の配備を行っています。(詳細は『 2. 4) 再び大きな地震・津波がきた場合の対策 』をご参照下さい。)
「福島第一原子力発電所・事故の収束に向けた道筋」の進捗状況について(平成23年12月16日)
政府・東京電力中長期対策会議 東京電力(株)福島第一原子力発電所1~4号機の廃止措置等に向けた中長期ロードマップ進捗状況(概要版)(平成24年1月23日)
(解説)放射性物質放出量の評価方法
【動画】第三弾「発電所内の放射線モニタリング」第2回 原子炉建屋からの現状の放射性物質放出量の評価(平成23年11月26日) 21:17