経営課題と社会課題の両面からアプローチ
次世代環境教育「尾瀬SDGs探求型スタディツアー」の目的と成果 第二部
2023/11/14

第一部では、当社の経営課題であるカーボンニュートラル社会の実現へ向けた事業の一つとして、尾瀬国立公園/尾瀬かたしなエリアの「ゼロカーボンパーク」登録をサポートし、その取り組み項目として「尾瀬SDGs探求型スタディツアー」を開発・実施していることをご紹介しました。
第二部では、ツアープログラムの内容と、プログラムの実施により地域の方々と尾瀬を一緒に守っていることについて、現地ツアーガイドを務める東京パワーテクノロジー株式会社 尾瀬林業事業所 ガイド・環境教育担当の斉藤 敦さん、第一部に登場した小暮 義隆さん(東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニットESG推進室)に聞きました。
東京パワーテクノロジー株式会社
尾瀬林業事業所ガイド・環境教育担当
斉藤 敦さん
2019年東京電力パワーグリッド株式会社群馬総支社より東京パワーテクノロジー(株)尾瀬林業事業所出向、2023年転籍
尾瀬林業事業所にて、尾瀬国立公園内での「ブナ植林地間伐体験」、「ヤマネ調査体験」、「ミズバショウ植え替え体験」、「SDGsバードコール作成ワークショップ」、「ライトセンサス調査体験」等の環境教育プログラムを地元の方々とともに創設、現在SDGs探求型ツアー等環境教育に関わる業務に従事。

尾瀬は学びがいっぱい!グループワークでアイデア探求
「尾瀬SDGs探求型スタディツアー」は、尾瀬の自然の中で地域の社会課題の解決を通してSDGsを実践的に学ぶ、主に中学生を対象とした2泊3日の学校向け企画ツアーです。“教えてもらうことからの学び”だけでなく、参加する子どもたち自身が自分の目で見て、体験し、そして考え、社会課題解決のアイデアをまとめること、これが探求型スタディツアーの大きな特徴です。
ツアープログラムは長年、尾瀬の行政・観光関係者や環境教育に関わる学識経験者のご指導を受け、2023年から構築・実践しているもの。
プログラムからは、日頃の生活では得られない学びや、地域課題を考える意義が浮かび上がってきます。ここでは、尾瀬の群馬県側に位置する片品村から入るプランを例にご紹介します。
尾瀬の概要や山での注意点をオンライン授業で事前に学習
ツアーへの参加を申し込んだ子どもたちは、ガイドが実施する事前のオンライン授業で、尾瀬の自然や歴史、山に入る上での注意点等を学びます。自然を傷つけず、また参加者自身の安全も確保するために必要な、基本的な知識を習得します。
学習で使用するノートで自然循環を学んでもらいたい
<ツアー1日目>
ツアーの1日目は、バスで片品村に到着した後、尾瀬ぷらり館内にある「尾瀬ネイチャーセンター」へ。展示を見ながら、ガイドの解説で尾瀬の環境や動植物のこと、湿原の植生復元等の保護活動について学びます。
続いて山へ入り、「ブナ林の間伐体験」と「ヤマネ調査」を行います。間伐は、密集した森林の健全化と光合成を促進し、植物に定着するCO2を増やす効果があります。また、環境に敏感なヤマネの生息状況は、間伐による環境変化の指標となります。このように一つひとつの体験がさまざまな学びにつながるよう、斉藤さんをはじめとするガイドの方々がプログラムを組み立てているのです。
「参加者に配布するフィールドワーク用のノートは、使用済みの尾瀬の木道を原料に使用した“尾瀬の木道ペーパー”で作られています。尾瀬の木道には、東京電力リニューアブルパワー株式会社が植林し育てたカラマツが使われていて、毎年約1.5km分が架け替えられます。こうしたところからも、資源循環のあり方を学んでいただけると思います」(斉藤さん)
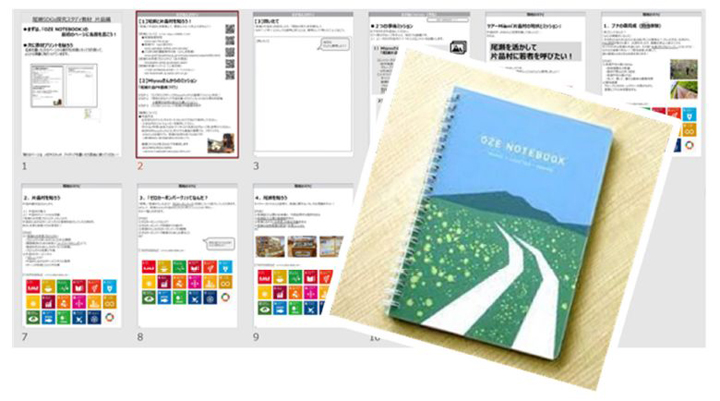
尾瀬の木道を原料にしたフィールドワーク用の「OZE NOTEBOOK」。
各ページに、事前学習にて配布された資料等を貼付します

森の指標動物といわれるヤマネ。一定数のヤマネを見つけることができると、間伐後の森が健全に保たれていることがわかる。

夜間にライトで動物を照らすと、ライトの光を反射し目が光ることを利用して、動物の頭数を数える調査法「ライトセンサス」を体験する子どもたち
宿泊場所は、東京パワーテクノロジーが運営する尾瀬の山荘の一つである「至仏山荘」です。ここで、探求型スタディツアーの“ミッション”が発表されます。若者や子育て世代のIターン、尾瀬に人を呼ぶためのアイデアといった地域の社会課題解決が、このツアーで子どもたちの探求するミッションとなります。
自分の目で見て学ぶために「あえて“教えない”」
<ツアー2日目>
2日目の朝、尾瀬山の鼻ビジターセンターを見学した後に、いよいよ尾瀬ヶ原のトレッキングへ出発します。子どもたちが自分の目で尾瀬を観察し、考える、絶好の機会となります。
「私たちガイドは、子どもたちに対してあえて“教えない”ことを心がけています。まずは子どもたち自身の目で見て、体験して、自分なりに考え、ガイドの説明を聞くのはその後でいいのです。自分で感じたことを大切にしてもらいたいと思っています」(斉藤さん)
昼食後は山荘に戻り、1日目に提示されたミッションにグループワークで取り組む「アイデア会議」が始まります。まずはファシリテーターのレクチャーを聞いて片品村の課題とSDGsとのつながりを意識しながら、グループごとに課題解決を考え、アイデアを大きな紙にまとめていきます。


2日間で学んだことや、SDGs17の目標・169のターゲットをチェックしながらプランを練り、自由な発想で課題に対するアイデアをアウトプット
村に採用された子どもたちのアイデアがツアー後に実現
<ツアー3日目>
最終日、山荘での朝食後に下山し、再び「尾瀬ネイチャーセンター」へ。いよいよ村役場や観光協会の方々に、グループで考えたアイデアをプレゼンします。
「2022年に実施した中学校のツアーでは、発表されたアイデアの一つが実際に村のPRイベントとして採用されました。これは、尾瀬の福島県側の玄関口である檜枝岐村にて横浜創英中学校さんが参加したツアーですが、『とかいでミニ尾瀬』というテーマで、尾瀬の自然に触れるイベントを都会で行うという企画です。イベントは2023年8月に実施されたのですが、提案した子どもたち自身もイベントに参加してくれました。自分たちのアイデアが社会課題の解決に結びつく体験を、より深いものにできたのではないかと思います」(小暮さん)


2023年8月に実施された「とかいでミニ尾瀬」。
東京スカイツリータウンを会場に、尾瀬の自然の紹介や地元物産の販売等をPRしました
子どもたちの心に、尾瀬と自然のことを残したい
上記は2泊3日の基本的なプランですが、小中学校からは1泊2日のライトプランへの要望や、大学では単位授業の一つとしてSDGsの要素をより深めたプログラムが取り入れられる等、ツアー内容は学校側のニーズや目的に合わせて調整されます。このように、学びの目的や環境が異なる子どもたちを尾瀬に迎え入れること等に、斉藤さん、小暮さんはどんな思いを持っているのでしょうか。
「未来の尾瀬を守ってほしいということはもちろんですが、ツアーでの体験を通して気候変動の影響や森と水源の関係といった自然循環を感じてもらい、皆さんの心の中に尾瀬と自然のことを残したいですね。何年か後にまた違う形で尾瀬を訪れたり、身近な山や海、他の国立公園等にも親しんでもらえたりしたらいいなと思います」(斉藤さん)
「これまで尾瀬を守ってきたのは、東京電力グループだけではありません。地元の方々と力を合わせて取り組んできたことが大変重要であると思っています。その地域の課題に、これからの時代を生きる子どもたち自身が取り組むことは、とても意義のあることです。そして、子どもたちがツアーで体験し持ち帰った学びを自分の日常生活にどう活かしていくのかが、非常に重要だと考えています」(小暮さん)
当社の経営課題である「カーボンニュートラル社会の実現」は、人と自然との持続可能な関係なしには成り立ちません。「尾瀬SDGs探求型スタディツアー」は、尾瀬の自然保護の意義はもとより、SDGs/ESG着想の具体化について次世代の子どもたちに受け継いでもらうためのフィールドでもあるのです。











