経営課題と社会課題の両面からアプローチ
次世代環境教育「尾瀬SDGs探究型スタディツアー」の目的と成果 第一部
2023/10/25

“広大な尾瀬ヶ原、周りを取り囲む2000m級の山々の大パノラマ、動植物との出合い等、他にはない特別な価値を持つ大自然”尾瀬国立公園といえばこうしたイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。TEPCOはその尾瀬国立公園全体のうち約40%の土地を所有しており、木道の設置や湿原の植生回復、公共トイレの維持管理といった活動を半世紀以上にわたり継続してきました。
そして今、尾瀬は東京電力グループにとって新たな価値を見出すべき場所になっています。東京電力グループは、「15 緑の豊かさを守ろう」をエネルギー事業に密接に関与するSDGs目標の一つに掲げ、尾瀬における自然保護活動をベースに生物多様性に配慮した事業活動を行っています。TEPCOの経営課題であるカーボンニュートラル社会の実現に向けて、地元・群馬県片品村の社会課題解決を視野に入れた次世代環境教育活動である「尾瀬SDGs探究型スタディツアー」の開発と実践に取り組む、東京電力ホールディングス 経営企画ユニットESG推進室の小暮 義隆さんにお話しを聞きました。
東京電力ホールディングス株式会社
経営企画ユニット ESG推進室
小暮 義隆
1992年入社。営業部門が長く、その後東京電力パワーグリッド株式会社群馬総支社を経て、2018年東京パワーテクノロジー株式会社尾瀬林業事業所長として尾瀬にて勤務。現在、ES(環境・社会)事業、自然資本・生物多様性に関わる業務に従事。
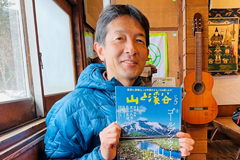
尾瀬の自然保護と観光産業を、持続可能にするために
群馬県片品村は、尾瀬国立公園の南西部、群馬県側に位置し、尾瀬への入り口となる鳩待峠や尾瀬ヶ原の大部分をその範囲に含んでいます。尾瀬を訪れる人々を中心とした観光が主要産業の一つです。その片品村が2022年4月、尾瀬国立公園/尾瀬かたしなエリアを「ゼロカーボンパーク」として申請し、登録されました。

「ゼロカーボーンパーク」とは、国立公園における電気自動車の活用・再生可能エネルギー導入などによる公園の脱炭素化を目指し、脱プラスチックなども含めた持続可能な観光地づくりを実現する、環境省主導の施策です。国立公園をカーボンニュートラルのショーケースとし、訪れる人に脱炭素型の持続可能なライフスタイルを体験してもらう場とすることを目的としています。

国立公園ゼロカーボンパークイメージ図
国立公園をカーボンニュートラルのショーケースとして、サステナブルな観光地づくりを推進する環境省の取り組み
出典:内閣官房HP地域脱炭素ロードマップ(概要)
ゼロカーボンパークは地元自治体が登録をする必要がありますが、小暮さんは「尾瀬かたしなゼロカーボンパーク推進担当」として、地元群馬県片品村や当社関連部門の人たちと共に登録を推進してきました。
「片品村さんは最終的に村全体の脱炭素化を目指しており、中でも主要産業の観光において先行して脱炭素に取り組もうと、今回の登録が行われました。私たちもそのための調査や取り組み項目の策定など、準備段階から協力しています」(小暮さん)
尾瀬国立公園/尾瀬かたしなエリアが登録した取り組み項目は、下記の3点です。
1)サステナブルツーリズム×ゼロカーボン観光の推進
2)脱炭素に向けた再エネの導入と省エネ推進
3)適切な森林管理等、CO2固定吸収量の確保
「尾瀬の入山口の拠点である鳩待峠では、現在、東京電力グループである東京パワーテクノロジーが管理・運営する鳩待山荘のリニューアル工事を行っています。尾瀬の山小屋では初となるオール電化を採用し、客室もインバウンドや登山者など、多様な旅のスタイルに対応できるよう計画しています。あわせて、その他の民間個人経営の山荘にも省エネ機器の導入を推進しています。また、東京電力リニューアブルパワー株式会社が施設・管理している木道には、FSC認証を受けた尾瀬戸倉の森の間伐材を利用して地産地消を推進するなど、東京電力グループが総力を結集してゼロカーボンパークの取り組みをサポートしています」(小暮さん)
FSC認証とは
FSC®認証は、責任ある管理をされた森林と、限りある森林資源を将来にわたって使い続けられるよう適切に調達された林産物に対する国際認証制度です。
尾瀬を体感し、尾瀬に学ぶ、探究型の旅から生まれる新しい価値
前述した取り組み項目のうち、「サステナブルツーリズム×ゼロカーボン観光の推進」に関する施策の一つとして企画されたのが「尾瀬SDGs探究型スタディツアー」。これは非エネルギー分野の事業であり、当社としてもこれまでとは異なる、新しい事業分野への挑戦となる取り組みです。どんなツアーで、どのような目的を持って企画されたのでしょうか。このツアーを主催する委員会のメインアドバイザーでもある小暮さんは、次のように語ります。
「尾瀬SDGs探究型スタディツアーは、小中学校・次世代層をターゲットに、従来の山荘利用に加えて『自然体験プログラム』『社会課題解決ワークショップ』を組み合わせ、探求型学習をテーマにした環境教育プログラムです。ゼロカーボンパーク実現施策の一部であると同時に、片品村が持つ社会課題の解決を組み込むことで、持続可能な社会をつくるSDGsの学びに紐づけていることが特徴です」(小暮さん)
そして当社にとっても片品村と協働する目的があると、小暮さんは3つのポイントを挙げました。
1)世界的なESGの潮流を踏まえ、当社の象徴的な自然資本である尾瀬をフィールドに、SDGs/環境教育をサービス展開する
2)コロナ禍で激減した山荘の利用者増加、特に若年層へのアプローチを強化する
3)当社の重要な経営課題であるカーボンニュートラル実現と連携させた、非エネルギー分野での付加価値サービスを提供する
「当社ではエリアエネルギーイノベーション事業室が『脱炭素先行地域』といった地域づくりや街づくりのプロジェクトを実施するなど、さまざまな形でカーボンニュートラル実現に向けた事業を展開しています。これをさらに非エネルギー領域の観光・教育などにも広げ、サステナブルツーリズム×ゼロカーボン観光を推進していくことが私たちESG推進室の役割です。その最初の舞台にふさわしいのは、ゼロカーボンパークに登録された尾瀬であると思っています。重要な経営課題であるカーボンニュートラルの実現に向け、そのモデルケースともなるゼロカーボンパークの取り組みを推進していきたいと思います」(小暮さん)
脱炭素先行地域について(環境省:脱炭素地域づくり支援サイト)
https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/preceding-region/
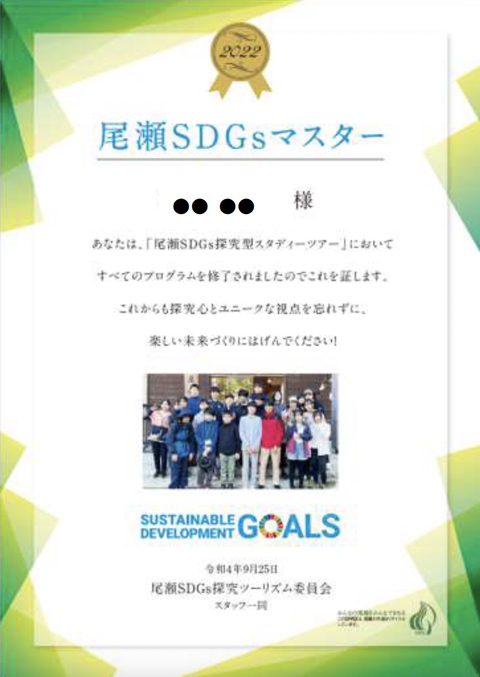
このツアーに参加する子どもたちは、事前レクチャーで尾瀬の自然環境や地域文化について学んだうえで現地に入り、尾瀬の自然に触れるトレッキングなど、2泊3日のさまざまな体験イベントに参加します。これらの体験を通して、提示された地域課題をグループで考え、その解決策やアイデアをイベント最終日に村長や観光課長が同席する場でプレゼンテーションします。【第二部】では「尾瀬SDGs探究型スタディツアー」の概要と成果の一部をご紹介します。











